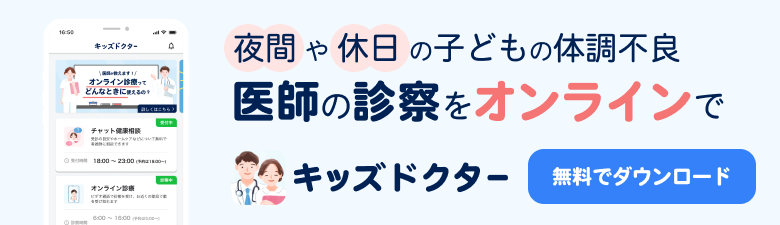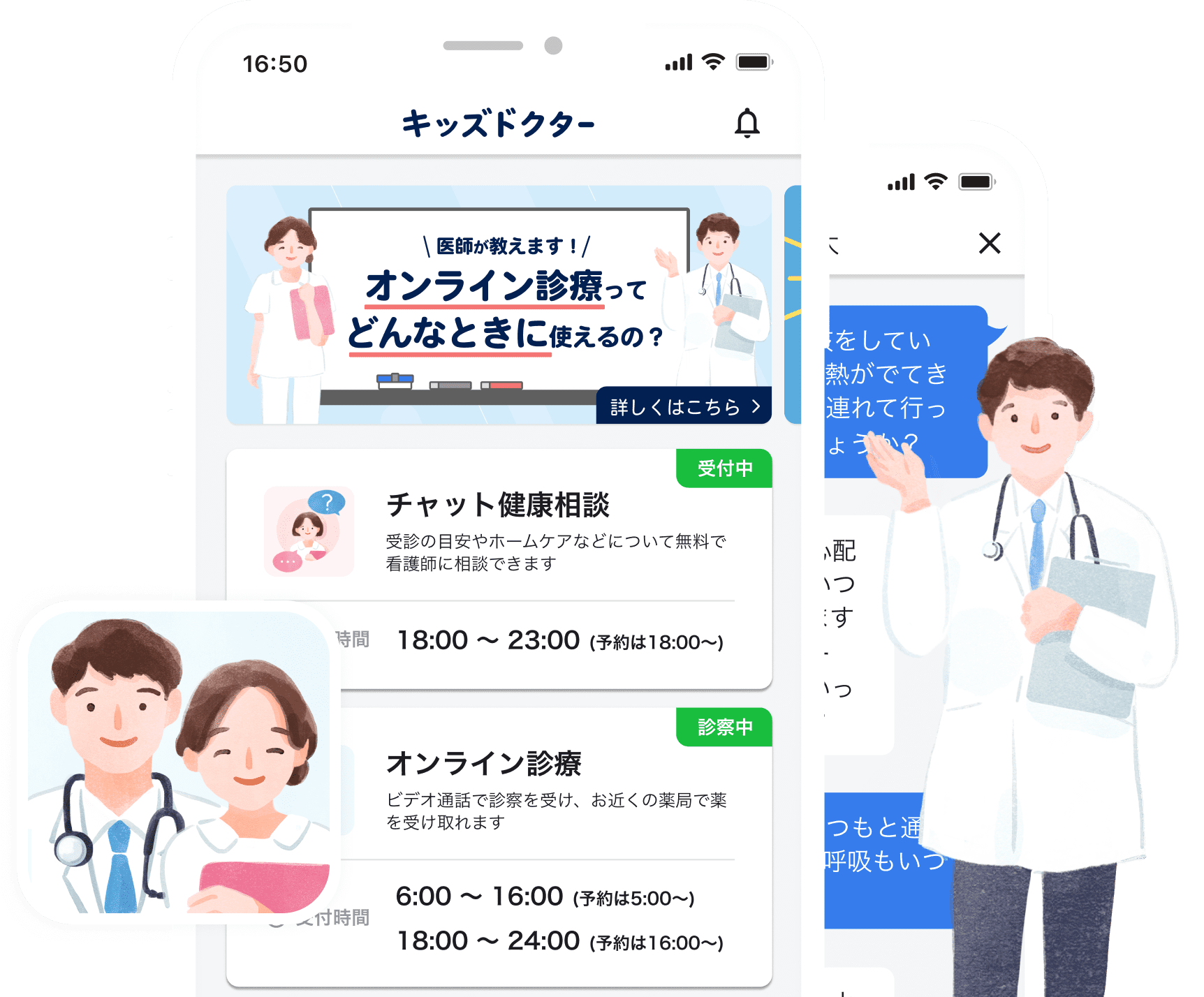プール熱・ヘルパンギーナ・手足口病の違いまとめ

夏になると子どもの間で感染が広がるプール熱・手足口病・ヘルパンギーナ。症状が似ていることもあり、混同しやすい感染症です。そこでこの記事では、それぞれの原因や症状、見分け方や違いについてまとめました。それぞれの感染症の基本情報からご紹介します。
プール熱の原因や症状は?
プール熱は正式には「咽頭結膜熱」といいます。アデノウイルスに感染することで発症します。
感染力が非常に強く、感染した人の咳やくしゃみなどの飛沫によって感染が広がるため、学校保健安全法で「第2種感染症」に指定されており、プール熱に感染すると一定期間出席停止になります。
主な症状は、38〜39度くらいの高熱、のどの痛み、結膜炎です。結膜炎にともなって、目の痛み・かゆみ、また充血や目やにの症状が出ることもあります。症状は4〜5日ほど続きます。重症化しにくい感染症ではありますが、中耳炎や副鼻腔炎、肺炎を合併することもあるため、注意して経過を観察する必要があります。
ヘルパンギーナの原因や症状は?
ヘルパンギーナはエンテロウイルスやコクサッキーウイルスが引き起こす感染症で、毎年5〜10月頃に流行する、いわゆる「夏風邪」のひとつです。原因ウイルスの種類が多く、何度も繰り返し感染することがあります。
主な症状は高熱とのどの痛みで、口の中に水ぶくれのような発疹ができます。発疹の痛みから食事や水分がとれず脱水を起こすこと、高熱で熱性痙攣を起こすことに注意が必要です。まれに無菌性髄膜炎を合併することもありますが、ほとんどの場合は後遺症もなく回復します。
手足口病の原因や症状は?
手足口病もヘルパンギーナと同じエンテロウイルスやコクサッキーウイルスが引き起こす感染症で、こちらもいわゆる夏風邪の一種です。感染力が高くウイルスの種類も複数あるため、1シーズン中に繰り返し感染することもあります。
手足口病に感染すると、口の中や手のひら、足を中心に水ぶくれのような発疹が出ます。発疹はおしりに出ることもあります。痛みやかゆみを伴うことはほとんどなく、1週間ほどで消失します。しかし口の中にできた発疹がつぶれると口内炎になり、痛みから食事や水分がとれなくなることもあるので、脱水症状に注意が必要です。
安静にしていれば数日で治る病気ですが、まれに髄膜炎や脳炎・心筋炎が起こり重症化することもあるので、元気になるまではしっかり経過を観察することが大切です。
プール熱・ヘルパンギーナ・手足口病の違いや見分け方のポイントは?
ここからは、プール熱・ヘルパンギーナ・手足口病の違いや見分けかたのポイントを解説します。
主要症状の違い
どの感染症も発熱とのどの痛みがあらわれます。プール熱はヘルパンギーナや手足口病と違い、目に症状が出るのが特徴です。
プール熱
- 発熱
- のどの痛み
- 結膜炎(目やに・目の充血・痛み・かゆみ)
ヘルパンギーナ
- 発熱
- のどの痛み
- 発疹
手足口病
- 発熱
- のどの痛み
- 発疹
発疹の有無、特徴
発疹が出るものとでないものがあります。また発疹の出るものは部位や出現の仕方、大きさに違いがあります。
プール熱
発疹は出ない
ヘルパンギーナ
- 水ぶくれのような発疹が口の中にできる
- 発疹の大きさは1~2ミリ程度
- 口の中の発疹がつぶれて、痛みをともなうこともある
手足口病
- 水ぶくれのような発疹が口の中、手のひら、足を中心にできる
- 発疹の大きさは2~3ミリ程度
- 発疹にはかゆみを伴わないことがほとんど
- 口の中の発疹がつぶれて、痛みをともなうこともある
発熱の有無、特徴
高熱が出るものと、出ないものがあります。高熱が出るものは発熱が続く期間に違いがあります。
プール熱
38~39度の高熱が4〜5日程度続く
ヘルパンギーナ
40度近い高熱が2~4日程度続く
手足口病
発熱はないことが多い。3分の1程度の確率で微熱が出る
感染しやすい年齢
どれも乳幼児がかかりやすい感染症ですが、特に発症しやすい年齢に違いがあります。
プール熱
5歳以下(大人も感染することがある)
ヘルパンギーナ
4歳以下(特に1歳代が多い)
手足口病
4歳以下
流行する時期
どの病気も夏季に広がりやすい特徴がありますが、流行のピークに少し違いがあります。
プール熱
6月頃から流行が始まり、7~8月頃がピーク
ヘルパンギーナ
5月頃から増え始め、6~7月頃がピーク
手足口病
6〜8月頃に流行し、7月下旬頃がピーク
プール熱・ヘルパンギーナ・手足口病は早めの受診を
プール熱・ヘルパンギーナ・手足口病は周りに感染を広げるリスクがあるため、症状があらわれたら早めに受診し、医師に指示をあおぎましょう。病院につれていくのが大変なときはオンライン診療を利用するのもひとつの手です。子どもの医療アプリ「キッズドクター」なら、子どもに慣れた医師の診察を受けられます。医師が必要と判断した場合は薬の処方も可能です。困ったときは検討してみてくださいね。
監修者について